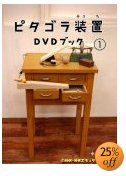2006年09月27日
「フラガール」

2006 日本
監督:李相日
製作:李鳳宇、河合洋、細野義朗
脚本:李相日、羽原大介
音楽:ジェイク・シマブクロ
出演:松雪康子、豊川悦司、蒼井優、山崎静代(南海キャンディーズ)
オススメ度:★★★★
映画を見終わるまでしらなかったが、これは実話だそうだ。舞台の常磐ハワイアンセンターは、今は名前を変えてスパリゾート・ハワイアンズ。ウェブを見る限りまったく時代遅れな感じない。へぇ、ちゃんと経営するってこういうことなんだなぁ。
それはともかく、映画の方も悪くない。レイトショーで1200円払って見る分には十分に納得。
まずキャスティングがいい。アイドル・蒼井優を中堅がガッチリ支え話題作りにしずちゃん……という構図は安易なようで、実はこれが具合に適材適所。先生のわりに踊れない松雪康子はそれはそれで骨細な街の女を演じるによかったし、しずちゃんもあくまでもしずちゃんのまま妙なハマり方で楽しかった。そしてなにより蒼井優がメチャクチャにいい。物語が進むにつれて少女から女に変わっていく表情と、エンディングに待ち構える気合いのフラダンス! あれを大画面で体験できただけでも映画館で見た価値はある。
ちなみにエンディングのダンスシーンは撮影・音響などのスタッフワークの部分でもテンションは高い。
気になったのはくどい脚本。基本がコメディー(?)なのに、あまりにも泣かせよう泣かせようとするポイントが多すぎて鼻につく。いや、もちろんそれでもそれなりに持っていかれて涙も流すのだけれど、だからと言って泣ける映画がいい映画というわけでもない。
12:07 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (0)
2006年08月16日
澤田知子展「MASQUERADE」
2006年7月15日(土)〜9月3日(日)
キリンプラザ大阪
入場料 300円
オススメ度:★★★★
お見合い写真でブレイクした《撮られる》写真家・澤田知子の新作シリーズはキャバ嬢○人。正方形のフレームで埋められた壁はさながらKPOから目と鼻の先に乱立する風俗案内所のよう。それにしても、あいかわらずちょっと無理のある……これじゃ完全に「ぽっちゃりさんの店」だ。それでもずっと見ているとこれは好きとかこれは嫌いとかがでてくるから確かに面白い。全員同じ人物だと分かっていても、無意識のうちに物語をつくっていってしまう。今回の展覧会のテーマは「顔」ということだけれど、むしろ真実を写さない(特に女性に関しては!)写真というメディアの特性の方が際立っているようにおもえた。この点において、確かに彼女は《写真家》であると言えるかもしれない。
ちなみに下の写真は自分が投票したキャバ嬢とお見合い写真。どうです?
07:47 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (0)
2006年05月26日
新しい耳
5月24日。ここ3ヶ月ほど使っていたiPodの標準イヤホンが壊れた。低音でバリバリ鳴る症状を考えると、またしてもバイク走行中の風圧にやられたのかもしれない。バイクを聞きながらの音楽鑑賞は、たえずこの問題がつきまとう。
っということで、梅田のヨドバシで新しいの買ってきました。
SENNHEISER MX500 WHITE(amazon)
天下のSENNHEISER、といっても値段は2400円と安め。音質は、中高音域が粒が細かく透明感があるのが特徴だが、低音も上品で落ち着きのある感じで悪くない。全体の再現性という点ではそれほど高いとはいえないけれど、粒の細かさに関しては国内メーカーのドンシャリ系とはまったく別物だし、クリアさに独特なインパクトもあって、相性があえばかなりお買い得。特に軽めのポップスを聴く人にはオススメ。確実に値段以上の音は鳴ってます。
17:20 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (0)
2006年01月09日
「皇帝ペンギン」
2005 フランス
監督・脚本:リュック・ジャケ
ナレーション:ロマーヌ・ボーランジェ、シャルル・ベルリング、ジュール・シトリュック
オススメ度:★★★
どう転んでも差し障りがないという点において、動物系ドキュメンタリーは作り手の悪意のようなものが浮き彫りになりやすい。しかし本作で浮き彫りとなったのは、むしろフランスという国の持つ詩的な垢抜けなさだ。ストーリー全体を包み込むような甘ったるいナレーションに、想像力を吹き飛ばすほどに違和感たっぷりのBGM…。
まぁ、それはそれとして映像的には撮影・編集ともに素晴らしい。観ているうちに体が本当に冷えてきた。
00:44 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (2)
2006年01月08日
「スチームボーイ」
2004 日本
監督:大友克洋
声優: 鈴木杏、小西真奈美、ほか
オススメ度:★★★★
さんざん長い間待たせたわりに世間的には酷評だった本作について、自分はかなり好意的な見方をした。なんといっても「AKIRA」をリアルタイムで10回以上観たのだ。どうしたってひいき目にならざるを得ない。もちろん「映画」という観点から冷静に判断すれば、それは確かに駄作だ。しかしこれは映画である以前に「OTOMO作品」であるということをお忘れなく。
一般的な評価通り、やはりストーリーテーリングは破綻している。とりわけスチーム城を舞台とした後半のドタバタ劇は、もはや物語とは完全に分離したテンションで進行し、そこに積極的に乗っていけなければ笑いどころすらない。「AKIRA」を体験していない世代には相当に辛い内容である。しかし、何度も言うが、あの「AKIRA」をつくった「OTOMO」の作品だ。設定が肥大化し、物語の枠を突き抜けて、作り手の偏執狂的なテンションだけが浮上してこそ、この作品には意味があるし、それこそを「大友らしさ」だと暖かく拍手を送るのが正解だろう。
あまり触れられることはないが、鈴木杏と小西真奈美の声優としての可能性も見所である。
04:58 | 固定リンク | コメント (1) | | トラックバック (3)
2005年12月28日
「映画クレヨンしんちゃん 嵐を呼ぶモーレツ!オトナ帝国の逆襲」
2001 日本
監督:原恵一
オススメ度:★★★★
物語を追っていくという作業に対しまだ未成熟な子供にとって映画がどのような「質」を保つべきかはいささか難しい問題だ。それは純粋な娯楽であると同時に、それを作ったり見せたりするする「大人」からのメッセージである。
「映画版クレヨンしんちゃん」シリーズについての噂は以前から知人より耳にしていたが、実際に見るのは今回がはじめて。てっきりアニメーションとしての完成度を期待していたのだけれど、なにをなにを、完全によくできた「映画」である。昭和にワープな設定もいいが、とにかくストーリーがよくできていて、その中に生きるキャラクターたちも血がかよう。子供に付き添った親たちが思わず涙したというのも納得だ。だからといって決して子供たちが取り越されるようなものでもなく、あくまでも「クレヨンしんちゃん」という本筋を守りながら。子供映画としての派手さもしっかり盛り込まれている。
これをリアルタイムに映画館で見た子供たちが、大人になって見直した時に、その物語の深さと作り手の高い意識に気づく。そういう意味で本作は非常に良質だ。
18:18 | 固定リンク | コメント (2) | | トラックバック (2)
2005年12月08日
「エレファント」
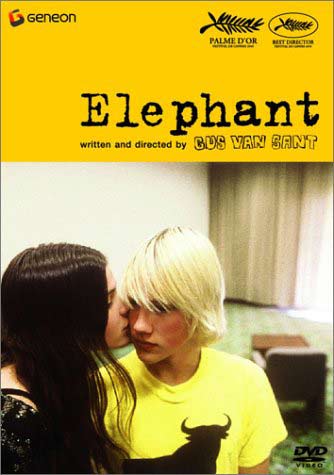
2003 アメリカ
監督:ガス・ヴァン・サント
オススメ度:★★★
1999年に起きた米コロラド州コロンバイン高校の銃乱射事件をモチーフに、「グッド・ウィル・ハンティング/旅立ち」のガス・ヴァン・サント監督が、事件が勃発するまでの高校生たちの一日を淡々と描いた青春ドラマ。2003年カンヌ国際映画祭でパルム・ドールと監督賞をW受賞。
「淡々と」が売りの映画だが、いささか「淡々としすぎ」であるように感じた。学生の日常生活が切り取ったように描かれていくのだが、はっきりいって前半はほとんどといって何も起きない。時間軸がちょっとずつずれていくような「メメント」的構成が今イチ効果的でないのも、原因はその「淡々さ」にあると感じる。構成を複雑にするのであれば、せめてそれぞれの伏線の接点はもっと映画的に描いてほしかった。ただこうした指摘を十分に理解した上でのこういう作品なのだということも十分に理解でので、つまるところ「そういう作品」であるということだろう。
個人的には、完全に見るタイミングを誤ったのが悔やまれる。かといってもう一度見たいかと言うと正直そうでもない。
12:25 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (0)
2005年12月06日
「笑の大学」
2004 日本
原作・脚本:三谷幸喜
監督:星護
出演:役所広司、稲垣吾郎
オススメ度:★★★★★
これぞ和製シチュエーションコメディー。大爆笑!といった感じの作品では決してないが、落語のような「クスッ」「ニヤッ」感が全体を包み、とても良質で心地よい。主演をつとめる2人はその実力とキャリアが正反対、コントラストが実に面白い。とりわけ役所広司の演技は文句のつけようがないほど完璧で、笑いに目覚めていく検閲官を見事に演じきっている。
12:45 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (0)
2005年07月07日
「スーパーサイズ・ミー」
2004 アメリカ
監督:モーガン・スパーロック
配給:クロックワークス、ファントム・フィルム
オススメ度:★★★★
「華氏911」でも思ったことだが、アメリカという国で生きる人々はどうやって民主的希望を持ちうるのだろうか。意識することすら難しいほどにすでにそこにある強大な商業主義と、そのことによってしか動かされることのない政治力。逆説的だが毎日ハンバーガーでも食ってなきゃやっていけないのかもしれない。
ドキュメンタリーとしても、エンターテイメントとしても、そこそこバランスの良い映画である。全体の構成がしっかりとしていて、ひとつのストーリーとして純粋に楽しめる。監督のモーガン・スパーロックは心身ともにそれほど「色」を感じさせない人物で、マイケル・ムーアのように個性でストーリーをひっぱっていくタイプではない。しかしだからこそある種のプロパガンダ性からちょうどいい距離が保たれているように感じられるし、結果的に私たちは作品そのものではなくそこで扱われるテーマについて考える気になるのだ。
この映画で扱われるマクドナルドはアメリカ的商業主義を語る上での象徴であり素材でしかない。結局のところアメリカ人はこの映画の中で暴かれたような極めて戦略的で無意識的な影響下の中で暮らしているということである。もはや誰もが知っていることだと思うし、それに対する有効な解決策などなかいのかもしれないのだが、やはり事実を突きつけられたことのショックは大きい。それもその事実が「肥満」「肝機能障害」「躁鬱」などという非常に身近な内容であるというのも説得力がある。ただ冒頭で触れたように、これを知ったところで果たして彼らには何らかの打つべき手が見つかるだろうか? むしろ一事が万事その調子であると状況を悲観したとき、「もういいや」と全ての問題を投げ出してマクドナルドに向かう可能性の方が大きくはないだろうか? アメリカ人のようでアメリカ人でない日本人の私はそんなふうに思うのである。
「とにかく知ってもらうことが大切」 以前、劣化ウラン弾をテーマとしたドキュメンタリー映画「ヒバクシャ」の監督・鎌仲ひとみ氏もそんなふうに言っていた。もちろんそのことは重要であるし、全てはそこからしかスタートしえない。しかしそこが問題解決の到達点ではないことも事実だろう。だとすればそこがドキュメンタリー映画、もしくは表現の限界なのか。そこから先に進むためには小林よしのりやムーアのように直接行動をおこす以外に手はないのか。だとすれば表現とはそもそも実効性を伴わないものなのか。それこそ投げ出すようなモノ言いでもうしわけないが、私にはあまりに問題が大きすぎてまだ分からない。それでも知ったのだから考えることは続けていこう。
ちなみにこの批評を書く前日に、最初の問いに対する具体的な解答が知人からあったので記しておこう。「大丈夫。西海岸と東海岸に住む一部のアメリカ人以外はみんな牛みたいなもんだよ」 あー、けっきょくそこかよー!!!
11:43 | 固定リンク | | | トラックバック (14)
「大(Oh!)水木しげる展」
会 期:8月4日(水)〜8月16日(月)
会 場:大丸ミュージアム 神戸
入場料:一般800円 大高生600円 中学生以下無料
オススメ度:★★★
荒俣宏と京極夏彦の共同プロデュース。水木しげるのこれまでの生涯を時間を追って追体験していくような内容。美術展というよりは回顧展(?)といった印象。各所に鏤められていた水木氏独特の語り口が、浮世離れした世界へ誘う。
時間が無くて残念ながら流し見だったのだが、単に漫画家・水木しげるに対してだけでなく、昭和30年代の紙芝居や貸し本システムが知れるという点においても面白い。あいかわらず原画展示という形態に関しては物足りなさは感じるが、商業展覧の企画としては十分の質と量。
機会があれば境港の記念館にも足をのばしたい。
11:42 | 固定リンク | | | トラックバック (9)
「栄光のオランダ・フランドル絵画展」
会 期:2004年7月17日(土)〜10月11日(月・祝)
会 場:神戸市立博物館
オススメ度:★★
あくまでもメインは「画家のアトリエ」である。このところのフェルメールブームにあやかった企画であるのは足を運ばずとも明らかである。しかしいざすべてがそこに向かうような展覧会の流れに身を投じてみると、逆に最後に肩すかしを食らうかもしれない。もちろんフェルメールがどうのこうのという話ではなく、それはむしろ絵画というメディアの取り上げ方の問題である。今どき「月の石」でもあるまいし、たかか数号の小さな絵に多くの人が殺到するのは、それ自体滑稽なことだ。そのことに気づくという意味において、同展覧は面白くなくはない。
個人的に興味を引いたのは、現在のわれわれの視点からして明らかに「おかしい」もしくは「上手くない」作品が多く出展されていたという点である。企画の内容的に、例えば遠近法の発見をまたぐようなかたちであったということもあるだろうが、それを差し引いても「おかしい」もしくは「上手くない」と感じられる作品が多かった。それらは大抵の場合、聞いたこともない作者もしくは明確な作者がわからないようなものであったが、それに比べてやはりファン・ダイクやルーベンスなどの有名な作家の作品は技術的にも表現的にも異なる次元にあるように感じられた。もちろん作家の知名度で評価するわけではないが、やはり名画と呼ばれるものは馬鹿にはできない。
ヤン・ファン・ダーレンの「バッカス」は違う意味でおかしかった。あれはただの酔っぱらいである。
11:42 | 固定リンク | | | トラックバック (30)
「デイ・アフター・トゥモロー」
2004 アメリカ
製作・監督・脚本:ローランド・エメリッヒ
出演:デニス・クエイド、ジェイク・ギレンホール、イアン・ホルム、エミー・ロッサム
オススメ度:★★
「インデペンデンス・デイ」のローランド・エメリッヒ監督による、異常気象パニック大作。背景はド派手だが、内容的には単なる親子モノ。設定などもずいぶんいい加減で、そのあたりが気をしだすとまるで楽しめない。むしろ映像だけで乗り切るのが○で、特にNYが津波に襲われるシーン等はCGだと分っていてもなかなかショック。妙に思わせぶりなエンディングは少し意味が分からなかった。
11:41 | 固定リンク | | | トラックバック (36)
「ハウルの動く城」
2004 日本
原作:ダイアナ・ウィン・ジョーンズ
監督:宮崎駿
出演:倍賞千恵子、木村拓哉、美輪明宏 ほか
オススメ度:★
PIXERの「Mr.インクレディブル」と迷いに迷ったあげく見に行ったがもう完全に大誤算。基本のストーリーテーリングの部分が無茶苦茶で、娯楽作品としてまったく成立していない。なんだかんだ言ってもそれなりに楽しめるミヤザキ作品の中にあって完全な駄作。さらに宣伝力の強さで押し通そうとしているのがミエミエで、この点では「CASSHERN」と大差なし。金がかかっている分まったくタチが悪い。
とにかくストーリーがまるで掴めない。もしかすると原作を読んでいればそれなりに理解できるのかもしれない。もちろんそういう映画があっても悪くはないと思うが、娯楽作品としての売り方をするのであれば物語を分かりやすくすることは最低限の義務であるように思われる。なにせ子供たちなけなしの小遣いを払って見るのである。そのあたりの誠意がまるで欠けている。どうした、ミヤザキ?
またキャラクターの設定が弱いのが気になる。主人公であるソフィーもハウルも最後の最後までいまいちキャラが定まらない。ハウルの弟子・マルクルや火の悪魔・カルシファーも重要な立ち位置にもいながらいったい何者であるのかがはっきりしない。美輪明宏演ずる荒野の魔女もさすがにもう飽たというのが印象。あ、ちなみにハウル役の木村拓哉は思ったよりもずいぶんマシで、ギリギリ合格点といったところ。
ただし評価できる点もある。たとえば映像表現の部分では、単に金をかけたということではなく、あらたな試みがいい形で実現されている多かった。ほとんど数種類のパターンを忠実に受け継ぐ日本アニメーションにおいて、トップでいながらなおも新しい表現に挑戦しようという同氏の心意気は十分に感じられた。
ただそういった部分を考慮しても、作品として決して評価できるシロモノではない。ネット上で見た感じでも一般評価もかなり厳しいようである。しかしその反面で大絶賛する連中も決して少なくない。はぁ? いったいどこをどう見ればそんな評価がだせるというのだろう。 既存の宮崎ファンなのか? それとも単に節穴なのか? いずれにしても作品そのものを冷静に判断できる「良き消費者」であってほしいものである。
ちなみに帰りに電車の中で、偶然にもハウル帰りの女子中学生2人組に遭遇。1人が重い口を開き「言いにくいけど、やっぱり今回はちょっとイマイチやったわぁ」と告げた。えらい!
11:35 | 固定リンク | | | トラックバック (40)
2005年06月29日
「電車男」
2005 日本
監督:村上正典
出演:山田孝之、中谷美紀、国仲涼子、佐々木蔵之介 ほか
オススメ度:★★★
言わずと知れた、2ちゃんねる発・美女とヲタクの純情初恋物語。
タイミングを逃すまいと撮り急いだ感はあるものの、思ったよりはずいぶんマシなのは、山田孝之の滑稽でありながらも切迫した演技のせいだろうか? 中谷美紀はあいかわらずきれいなお姉さんで、もちろん美化されているとはいえ、エルメスに対する想像をいい意味で掻き立てる。
内容的にはオリジナルを忠実に再現しようとしたためいくらか無駄なシーンが目立つ。ヲタク3人組の戦闘シーンなどはもうすこし熟考すべきだったかもしれない。とはいえ、ネットの上でテキストを中心に繰り広げた世界をこれまで無理なく映像化した点(特に絵文字のあつかいがなかなか面白い)は十分に評価できる。ネットという部分の親近感で若干ひいき目で見れば十分に楽しめる。
11:31 | 固定リンク | | | トラックバック (26)
2004年12月29日
「ターミナル」
2004 アメリカ
監督:スティーブン・スピルバーグ
出演:トム・ハンクス ほか
オススメ度:★★★
本当に「可もなく、不可もなく」。取り立てつまらないわけでもないが、取り立てて面白いわけでもない。設定の面白さを除けばストーリーにそれほど魅力があるわけでもなく、かといって全くないわけでもない。なんとなく見始めて、1時間半後になんとなく終わる。そんな印象。よって残念ながらそれほど書くこともない。
ただひとつ興味深かった点は、この作品の持つ映画特有のスケース感だ。あまり考えたことがなかったが、映画のスクリーンと空港のターミナルは共に人の身の丈に対して心地よくデカいという点において相性が良いようだ。観賞後になんとなく本当に空港にいたような感覚にはなる。このあたりがスピルバーグ品質なのかもしれない。
11:32 | 固定リンク | | | トラックバック (12)
2004年10月06日
アトリエ・ワン「街の使い方」展 - 小さな家の設計から大きな年の観察まで
2004年10月2日(土)〜12月5日(日)
キリンプラザ大阪
キューレーター 五十嵐太郎(建築史・建築批評家)
入場料 700円
オススメ度:★★★
アトリエ・ワンの塚本由晴氏は、以前IMI主催で美術家の中村政人との対談で一度だけ話を聞いた。まるで建築家と思えないまるで大学生のような風貌と、飄々とした口調ながら鋭い指摘をする様子がとても印象的。目的も方法も違うが、美術という枠組みがこれまでにもまして知的に解体されようとしていている昨今において、彼らから学ぶべき物はおおいように思われた。
意外な事にアトリエ・ワンにとって今回は初の個展。内容は同ユニットの設計した狭小住宅「ミニ・ハウス」をカヤで1/1再現、その中で書籍や映像などの資料が展示されるというもの。空間性の体験という意味では面白いが、やはり見せ方としてはいささかものたりない。まぁ、展覧会というスタイル自体、建築の文脈から外れたもなのだから仕方ない。それでも彼らの仕事、というよりユニークな視点そのものの全風景を眺めるにはいい機会だった。
活動の部分で面白いと思ったのは、彼らの活動の中心がリサーチにあるということ。これは塚本氏が研究者であるという立場を考えると当然のなのかもしれないが、それ自体がひとつの作品として成立しているのは興味深い。もちろん彼らの仕事の本質は建築設計なのだが、もはやそれすらもプレゼンテーションの一部でしかないと感じてしまうほど、彼らの存在にはブレーンとしての意味合いが強い用に感じられる。
11:35 | 固定リンク | | | トラックバック (40)
2004年09月24日
トヨダヒトシ「スライドショー/映像日記」
2004年9月23日(祝)〜26日(日)
[NA.ZUNA part 1]・[NA.ZUNA part 2]・[The Wind's Path]
CAP HOUSE 神戸(神戸)
1,000円(1ドリンク付)
オススメ度:★★
スライドショーにデフォルトでBGMがつくようになったのは、もしかするとAppleの残した悪しき習慣かもしれない。時間軸に写真を並べてそれを投影する、それだけで写真はひとつの流れの中で新しいストーリーを語りだす。別に特別なことでも何でもないのだけれど、そういうことを当たり前をするのが実は一番難しい。この点においてこの作家は極めて潔い。ただしその潔さが作品を作品として成立させるべく正しい方向に導いているかどうかは微妙なところである。
誤解も含めてテーマは「旅」である。すくなくとも私にはそのように思えた。見知らぬ土地で見知らぬ人々とふれあうことで目覚める視線があることは、すでに誰でも知っていることである。それをいまさら作品として見せる、もしくは見せられるということに対しての疑問は多い。それにつけて昨今の写真ブームの後に、それでもなお作品化が可能な写真とはいかなるものか。写真という表現形態が本質的にメディアとの関わりを逃れられないとするならば、それについては潔いトヨダ氏に答えてほしかった問題である。あとプロジェクションという手法についてももう少し説得力が欲しかった。作者説明では「そこに有るのに触れる事が出来ない距離感」とのことだったが、個人的には納得するにはいたらなかった。
ただ、そういったことを考慮しても、スライドショーをひとつの表現形態として突き通そうとするトヨダ氏の潔さについては今後の期待もこめて評価したい。
11:40 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (31)
2004年09月04日
「6人の作家/articulation 2004」
2004年9月4日(土)〜25日(土)
今井祝雄・植松奎二・河崎晃一・倉貫 徹・藤本由紀夫・百瀬 寿
ARTCOURT Gallery(大阪・天満橋)
入場無料
オススメ度:★★★
作品の評価において「凛とする」という言葉を用いたのは「ノンポリおおさか・(展)」でご一緒した松村 アサタ氏だったが、それは同グループ展を言い表す上で適切な言葉のように思われる。極めて「凛」とした展覧会。
すでにキャリアの長い作家たちによるグループ展である。そこにコンセプト上の安易なすりよせなどは感じられない。むしろそれぞれがそれぞれの仕事を全うしているように感じられる。「凛」というのは、その結果として浮き上がってきた印象だ。それこそが本展をグループ展として成立させているように感じる。
中でも植松奎二と藤本由紀夫の力は大きいように思われるが、このあたりは好みの問題かもしれない。逆にいまいちピンと来なかったのは大量のチラシを丸めた今井祝雄のインスタレーションで、この作家に関しての予備知識はとくにないが、一見すると作品そのものの力より空間に頼る部分が大きかったように感じられた。河崎晃一の小さめの造形は、本人を存じているせいだろうか、いつも人物とのギャップが興味深い。倉貫徹の水晶を用いた平面は、単純な構図の中に素材の差異による独特の緊張感があって興味深かった。
11:46 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (38)
2004年08月22日
東海テレビ「女医・優〜青空クリニック」
原 作:軽部潤子「青空クリニック」(講談社Kiss連載中)
脚 本:深沢正樹、大原久澄
制 作:東海テレビ放送、国際放映
時 間:毎週月曜〜金曜日 13時30分〜14時00分
出 演:木内晶子、岸田今日子、西興一朗、大浦龍宇一 ほか
オススメ度:★★★
可愛い以上、きれい未満。アイドル以上、女優未満。いってみればそういう微妙さについて心奪われるのは、何かのコンプレックスのあらわれなのか?
それはともかく、昼ドラ「女医・優〜青空クリニック」の木内晶子はいい。芸能人としての彼女の立ち位置もさることながら、あの若さで若き女医という設定がかなり不自然で素敵だ。個人的にかるく鷲掴みである。ここでは木内本人よりむしろ彼女に主役を与えた、企画サイドの愛を評価したい。
ちなみに木内晶子の所属するイザワオフィスは渡邊プロ系列で、ドリフターズ、いしだあゆみ、竹脇無我、小泉孝太郎などが所属。
11:50 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (36)
2004年08月20日
トワ・エ・モワ「ベストコレクション」
発売元:東芝EMI
発売日:1992年08月26日
オススメ度:★★★★
以前からずっと気になっていたトワ・エ・モワのベストを図書館で入手。公共サービス・フル活用。
今風にいえばソフトロック。なにより直球のユニゾンデュエットが新しい。清らかで芯のある山室英美子のソプラノとそれを優しく支える芥川澄夫のテナーは、互いにけっこう癖があるが不思議と相性がいい。和製カーペンターズと称されることもあれる彼らだが、日本人にとってはむしろ本家よりも洗練された世界観がそこにあるように思われる。とくに「或る日突然」を文句なしの名曲、本質的な価値観の部分でまったく色あせていない。
山室は82年よりソロ活動を開始。2002年にも「I'm Here〜永遠の詩」をリリースしている。芥川はボイストレーナーとして活動中。
11:49 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (10)
2004年08月15日
西平 直「シュタイナー入門」
出版年:1999年
出版社:講談社(講談社現代新書)
定 価:660円
オススメ度:★★★
ここ最近、シュタイナーについて幾分かの興味を持っている。きっかけはNHKで数年前に放映された「エンデの遺言」というドキュメンタリーで、ミヒャエル・エンデの経済に対する指摘にある思想的背景として触れられていたのがきっかけである。シュタイナーというと妄想癖の強いオカルティストで、いわゆる精神世界への窓口的な人物としてのイメージが強い。それが経済という極めて実社会的なテーマにつながりうるという点が興味を引いた。そこで実際にいくつかのシュタイナーに関する手引書のようなものを読んでみたのだが、これが私にはどうもよろしくない。その内容は極めて専門的な哲学的視点から書かれたものであるか、それとも精神世界まるだしのまさにオカルトと呼ぶにふさわしいもののどちらかである。
本書はその中においてシュタイナー初心者に対し極めて分かりやすくその思想と人物像を紹介している。もちろんその思想の特殊性において、その全体と核心を十分に理解しうるには物足りなさを感じる内容である。また筆者が執筆者として完全な客観性をたもっているかという点に関してもいささか問題は否めない。しかしながら筆者が「入門以前」と指摘するように、シュタイナー思想のその導入への糸口を見つけるためにはそれなりに有効である。とりわけ筆者と学生の間で実際にやり取りされたいくつかのエピソードは、入門者の抱く極めて初歩的な問題の意味を解決するには役に立った。
しかしながら実際にシュタイナー思想そのものに触れてみると、その怪しさというか荒唐無稽さに圧倒される。これは表層的な部分だけをかすめとった上での安易な批判ではない。むしろそう言われることが思想家として生きたシュタイナー自身の宿命であるとの理解によるものだ。この点については筆者も触れているが、もし仮に彼が芸術家として生きたのであれば、現在のような誤解の上に立たされることはなかったはずである。人生観、世界観、宇宙観……それを自らのイメージの中で膨らまし具体化することは芸術家にとってごくごく普通の作業である。しかし彼はそれをあくまでも哲学的文脈の中で展開しようとした。その結果、彼の思想そのものがオカルトとして扱われてしまっていることは、その内容の善し悪しはともかく残念なことだ。
ただ、彼がもし芸術家だったらという仮定を実際に想定した場合、その思想がどれほどまでに広く影響を与えたのかという点に関しては、私は私の立場を持って冷静に考えたいと思う。例えば、近年ボアダムズのEYE氏が「B∞DOMS」で具現化した宇宙のイメージが、現実的な社会的影響力としてどれほどの力を持ちうるかはここで説明する必要もない。芸術とはそういうところに位置していることが前提だからだ。
11:34 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (28)
2004年08月14日
デュークエイセス「ゴールデンベスト20」
発売年:1988年
発売元:東芝EMI
オススメ度:★★★
デュークエイセス20曲入りベスト。録音自体は80年代のものが中心かと思われる。NHK「みんなうた」の「シューティングヒーロー」や名曲「筑波山麓合唱団」はデュークエイセスのコミカルな一面が垣間みれる。それにしても何を歌ってもデュークエイセス風に消化してしまうあたりは流石である。ちなみに「筑波〜」は1969年の紅白歌合戦に出場した際に歌われている。
11:49 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (11)
モダンチョキチョキズ「別冊モダチョキ臨時増刊号」
発売日:1994年06月22日
発売元:キューンレコード
オススメ度:★★★★
モダチョキの2.5枚目(?)のアルバム。5曲の新曲、5曲のリミックス、5つのコントで構成される。
ビッグバンドとしてのイメージが強いモダチョキだが、このアルバムでは打ち込みものも披露。抱え込むメンバーの豊富な才能の深さが伺い知れる。とりわけコアメンバーである長谷部信子(Key)は「天体観測」「自転車に乗って,」でメロディーメーカーとしての才能を発揮。70年代生まれにとってまるで原風景のようなメロディーと、抽象的でありながら胸を刺す歌詞は、まさに秀逸。ちなみに長谷部は後に巻上公一とユニットをくんだりソロアルバムをリリースしたりしているが、2001年以降は表立った動きはない。またいかにもモダチョキらしい大風呂巨編「THE 絶望行進曲」は作詞に安田謙一の名が。
同バンドの活動の中ではいさかか途中休憩的な内容だが、それでも聞いておくべき曲は少なくない。振り返っても、まだまだ味わい深いバンドである。
11:48 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (34)
「タクシードライバー」
1976 アメリカ
監督:マーティン・スコセッシ
脚本:ポール・シュレイダー
音楽:バーナード・ハーマン
出演:ロバート・デ・ニーロ、ジョディ・フォスター、シビル・シェパード、 ピーター・ボイルほか
オススメ度:★★★
予想以上に脈絡のない映画。いや、そうではない。問題は時代性である。カンヌ映画祭グランプリほか数多くの賞に輝いた名作であるということを前提にして考えれば、今さら「現代都市に潜む狂気と混乱」などと分かりやすい言葉を並べたてたところで理解はほど遠い。70年代のニューヨーク、そこで生きるベトナム帰りのタクシードライバー。このことことの持つ意味の大きさを知らなければ、おそらくこの映画の持つおもしろさは見えてこないのだろう。もちろんこれも推測にすぎない。
時代性を逃れない全ての表現はある種生ものであるわけで、当然リアルタイムでみるのが一番いいのは言うまでもない。とりわけ映画というそれ自体がメディアとしての広がりを持つ形態であるならば当たり前のことだ。だからわれわれはその時期を外して後に作品と向き合う場合、多少なりとも時代性に対する態度を問われる。あえてここで「態度」とと言ってみたのは、例えば小西康陽のように時代の差異をそのまま受け入れて消化するようなスタンスもあり得るからである。実際、本作は表層的な部分だけすくいあげてオシャレと言わしめるような側面も持っていて、下手するとリバイバル・ファッション的な視点で受け取ることも可能である。ただ実際のところわれわれは、作品がそもそも持っていた意味なり価値を知ってみたいと願うわけであり、一鑑賞者としてはなかなか小西氏にはなれない。難しい点ではある。
なお、これが遺作となったB・ハーマンのスコアがかなり効果的に使われている点は特筆に値する。
11:43 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (9)
2004年08月06日
市制50周年記念 宝塚観光花火大会
日 時:8月6日(金)・7日(土) 19:45〜20:30
会 場:宝塚市武庫川観光ダム一帯・武庫川河川敷
打上数:2日間で約4,000発
オススメ度:★★★★
もはや自分にとっては当たり前になってしまったが、阪神間の数ある花火大会の中でも宝塚の観光花火大会は他とはかなり違った趣きがあって面白い。音楽と花火によって描かれるかなり情緒的な世界は、カタカナで表されるところの「タカラヅカ」が強く意識されたものであり、よって良くも悪くも「宝塚的」だ。もちろんそれは歌劇同様好みの分かれるところである。ただ、宝塚で生まれ育ち、今なおそこに住む私には、ファミリーランド亡き後の宝塚にささやかな記憶の断片を残すといった意味において、きわめて肯定的にとらえられる。
今年のテーマは「心に咲く花火の競演 鏡花水月」。「オープニング」「微笑」「涙」「叫び」「眠り」「エンデング」の全6章で構成。このあたりは歌劇よりもむしろ手塚治虫の影響が伺える。中でも「叫び」の章におけるプリミティヴな世界観は「火の鳥」や「ジャングル大帝」などで描かれたものそのもののようにも受け取れる。考えてみれば夏の花火大会に「涙」や「叫び」が似つかわしいはずもなく、むしろそこには「手塚の生まれ故郷」としてのイメージを打ち立てようとする同市の思惑が見え隠れしているようにも思える。
ただそんな憶測を抜きにしても、本花火大会はかなり見応えがある内容だ。打ち上げ数こそ少ないが(2000発)、テンポのいい展開と工夫を凝らした演出で、いわゆる花火大会というよりはむしろ何かのショウをみているような感じになる。興味深いのはやはり花火そのものによる表現の可能性で、実際はそれほど真新しい花火が上がるわけでもないのだが、組み合わせとタイミングによってかなり具体的なイメージを想起させられる。あまりこういったモノ言いはしたくないのだが、大衆芸術における表現としては十分にその質を保っているように感じられた。なお、花火を見る限りではよく分からなかったが、「高度なシンクロ演出が可能なコンピューター点火と 暖かみのあるアナログ点火のハイブリッド演出(公式ウェブより)」が採用されているとのこと。来年はこのあたりに注目してみたい。
今年は風向きもよく煙もほとんど気にすることなく楽しめた。観覧は西駐車場観覧場(有料/1dつき500円)がオススメである。
11:46 | 固定リンク | | | トラックバック (10)
2004年08月05日
鳥取1泊2日の旅 2004
交通手段:車
ナビゲーター:鳴海健二
コース:ベニ屋(カレー&インド氷) - 白兎海水浴場 - 健康いちばん・因幡っ子(定食) - 吉岡温泉館 - 鳴海家(宿泊) - 鳥取砂丘 - 戸倉滝流しそうめん
オススメ度:★★★★
限られた時間の中で知らない土地を楽しむ旅行というイベントにおいて、編集はきわめて重要なセクターである。それがひとつのパッケージングされた形として提供されるものはすなわちツアー旅行だが、へそ曲がりな消費者であるわれわれはそういった旅のあり方について背を向ける傾向にあるようだ。もちろん無編集で楽しめるならそれはそれで別の意味ですばらしいのだけれど、よく作り込まれたツアーというのもなかなかいいものである。たまには人の船に自分からのってみるのも悪くない。
たった1泊2日の旅行の内容がこれほどまでに充実していたことの理由は、ひとえにナビゲーターが元地元民だったということにつきる。今回彼は事前に入念なコースをきめたわけではなかったらしいが、それでもこれほど盛り沢山かつ無理のない内容はさすが引き出しの多さを感じさせる。土地を知っているということはまさにこういうことが出来てしまうということなのだと思う。
旅中、一貫して印象的だったのは砂である。それは単に海と砂丘にいったというだけのことなのだけれど、その感覚は懐かしく新しい。残っていく記憶は実はそういうものだったりする。あ、あと因幡っ子か。
01:37 | 固定リンク | | | トラックバック (32)
2004年08月01日
「ゲロッパ!」
2003 日本
監督&脚本:井筒和幸
出 演:西田敏行、常盤貴子、山本太郎、岸部一徳 ほか
井筒和幸監督は初めての鑑賞。微妙に安い脚本と役者が完璧で、良質な日本の大衆映画といった感じ。テレビで管を巻く同監督に対して実のところそれほどいい印象は持っていなかったが、その安さがただの安さでないことを知る。他の作品にたいしても十分興味をそそらせる。
このところ役者としての幅が急激に広がりつつある西田敏行はチンピラの親方がまるでハマり役。相方役の岸部一徳ともいいコンビだ。山本太郎は相変わらず素がよく栄える。
11:44 | 固定リンク | | | トラックバック (11)
西野康造「空のかたち」
2004.7.10(土)〜 8.29(日)
ARTCOURT Gallery(大阪・天満橋)
入場無料
オススメ度:★★★★
自分が言葉を使った仕事をしているせいもあるだろうが、私は既存の美術的言語に対してどうも斜に構えて見ているような節がある。ここで言うところの言語とは表現における形態のことだが、とりわけ彫刻に対するそうした想いは強い。例えば、無骨な鉄の固まりがほんの少し反りながらそこに存在しているということ。その正当性についてここで触れることではないが、ただそれが表現として優れた言語として成立しているかということに関してはかなり疑問だ。
西野康造という作家に対する予備知識はない。ただ今回の作品だけをみてその仕事を自分ありに評価するとすれば、前述の言語という意味合においてそれは抽象的な形をとっているにもかかわらず非常に雄弁だった。「空のかたち」といういささかスイートなタイトルも、本体の的をえながらもいい具合で印象を中和させている。こういう作品にたまに出会えるので、やっぱり彫刻もそれほど無視はできない。
高さ10メートルをこえる輪や複雑に連結されたモビール状の作品。大きいわりにアルミやチタンといった素材のせいか、いい意味でそれほど重量感はない。細いフレームで組み合わされた作品も、素材自体のしなやかさによって、空調の風を受けて振動している。丘の上にあって風になびくような印象。いわゆる金属彫刻に対する印象がここちよくずれていくのがおもしろい。
これらの作品からわれわれが受け取るものはかなり具体的な情景やシーンである。作品の存在の仕方自体を考えればそれほどの新しさも驚きもない。ただ、あえて遠回りな手法をとりながら最後にスイートな情景に回帰していくという面白さは美術としてひとつの正解だし、なによりその分かりやすさに私は純粋に心を動かされる。
01:40 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (11)
2004年07月31日
近藤晃弘「死線上のバンパイア」
2004.7.12(月)〜 7.31(土)
ギャラリー wks(大阪・西天満)
入場無料
オススメ度:★★
近藤晃弘、79年生れ、大阪芸術卒の若い作家。
内容はホワイトキューブの会場が血しぶきで染められているというもの。意外にもギリギリのところでグロテスクではない。むしろ赤く染め上げられた空間には不思議と閉鎖感がなく、ほんの少し心地いい。ロケーションも考えればとあるマンションの一室の惨殺劇となっても不思議はないが、どこか最後の一線でそういった下世話さを踏みとどまらせている。
ただし、やはりこういった単純な構成のインスタレーションは、よっぽどでないと物足りなさを感じずにはおれない。まぁはっきりいえば安易である。がんばっていただきたい。
なお、ギャラリーwksには初めておとずれたが、マンションの11Fでもここまでできるかとちょっと関心。アクセスは決していいとはいえないが、スペースとしてはなかなか面白い。後日、ゆっくり訪れよう。
01:39 | 固定リンク | | | トラックバック (5)
田名網敬一 × 宇川直宏「DISCO UNIVERSITY」
2004.6.5(土)〜 8.1(日)
KPOキリンプラザ大阪(大阪・心斎橋)
一般700円/学生500円(中学生以下無料)
オススメ度:★★★
宇川直宏という人についてのイメージは、その名前との出会いから、いまだにMOM'N DADの主催者という印象が強い。20分ほどのハナタラシのものを壊すだけのライブと、ディック・ハイマンなどのスペースエイジ・バチェラーパッド・ミュージックの抱き合わせ(?)コンピを私はリアルタイムで手に入れ、そして今でも持っている。
田名網敬一と宇川直宏のコラボレーションということなので、てっきり一緒にペインティングをしたりコラージュしあったりといった内容を想像していたが、実際は田名網氏の過去の作品の展示を宇川氏がディレクションするというもの。そういう意味では若干期待をすかされた感じではあるが、田名網氏のことをほとんど知らなかったので、全貌を知るいい機会となった。
作風に関しての詳細な解説は省こう。個人的にはああいった70年代を感じるような毒っけのあるイラストレーションはそれほど好きではないが、もはやそういった好みをどうのこうのいう以前に、作品の多さと、個々の作品持つ情報量に圧倒された。こういった作品に大して、もはや解釈という行為はそれほど意味をなさないように思う。作家の爆発するようなエネルギー量や、それによって生まれる疾走感のような感覚は、もはや理性の領域でうけとめられるべきではないだろう。この点に関しては宇川氏にも同じことが言えるかもしれない。とにかく失踪する2人である。
宇川氏による展覧会全体のディレクションは正直少し物足りなさを感じた。会期中にクラブイベントを実際にそこで行うといった試みは風俗的な文脈を美術に持ち込むと言った意味では評価できたが、展示そのものにはあまりそれが見受けられなかった。
01:38 | 固定リンク | | | トラックバック (10)
2004年07月25日
山崎つる子「リフレクション」
2004.7.12(月)〜 7.31(土)
芦屋市立美術博物館
一般500(400)円、大高生400(320)円
オススメ度:★★★★
具体というと身体性を重視したような派手なアクションやハプニングといったことを連想する。しかしが同グループの一側面でしかないということは、すでに先の「具体回顧展」(兵庫県立美術館)において語られたことである。今回の山崎つる子展はその内容をあらためて立証するためのいい機会だ。
かつて"confusion"という言葉によって表された山崎つる子の抽象絵画は、今もなお十分に混乱を極めているように見える。あらゆる要素において安定と調和を拒否するような作品からは、もはや禁欲的なものすら感じられる。デタラメであるために繰り返される葛藤と省察。その態度はある意味で私たちが持っている具体のイメージと正反対のものであるように思える。ただ面白いことに、そこからなにかから解き放たれたいとする苦痛はまったく感じられない。
作品の変遷もなかなかデタラメである。突然「title」(もちろん「untitled」ではない)という題名で具象画を描いてみたり、かと思えば転がるビー玉に光を通すような普通にきれいな作品もある。あまのじゃく、そんな言葉をイメージする。いつも対局するものの間を行き来しながら、けっきょく何にも束縛されないお嬢様。そういえば彼女は芦屋生まれの芦屋育ち、清心女子出身のねっからのお嬢様だったか。まぁ、特に関係はないだろうが。
展覧は彼女の活動を理解する「redlection」「color」「confusion」「metallic」「stripe」「title」の6つのキーワードによって構成。あえて異なる次元で視点を混乱させたのも意図的かもしれないが、そこはもうちょっと系統立ててみてもよかったかもしれない。
01:39 | 固定リンク | | | トラックバック (14)
2004年07月19日
「イナフ」
2002 アメリカ
監督:マイケル・アプテッド
製作総指揮:E・ベネット・ウォルシュ
脚本:ニコラス・カザン
出演:ジェニファー・ロペス、ジュリエット・ルイス 、テッサ・アレン ほか
オススメ度:★★
いわゆるDVモノ。サイコサスペンスかと思いきや後半はアクションまっしぐらで少し大意表をつかれたが、ストーリーそのものには新しさが感じられなかった。細かい設定が甘くて不可解に思う点もいくつかあったが、まぁそれはエンターテイメントというころでよしとすることにしよう。
主役のジェニファー・ロペスはハマっていてなかなか。暴力亭主役のビリー・キャンベル と主人公の元恋人役のダン・フッターマンが微妙にかぶるところが気になる。
なんとなくビデオを借りてサラッと見るにはいいかもしれないが、映画館で2時間近く腰をすえて見るのはすこしむずかしい。
01:36 | 固定リンク | | | トラックバック (38)
2004年07月10日
「エンタの神様」カンニング
2004.7.10 sat 22:00〜
日本テレビ
オススメ度:★★★★
メインカルチャーとサブカルチャーの境界線にあるものは何か。その境界線をマスメディアはどうあつかうか。あいかわらず解決されない問題……
「エンタの神様」(NTV)でカンニングというお笑いコンビを見た。業界や観客に対してある種自虐的とすら言えるような罵声を大声でがなり立てるというかなり異色の芸風で、形態としてはコントや漫才というより演説や即興劇に近いかもしれない。以前関西ローカルの番組に出演していたのを見てその時もなかなか忘れられない印象だったが、7月10日同番組で繰り広げられたものはそれをはるかに超えてショッキングにすら思えた。
おおまかな内容は以下の通り。キレ役の竹山がいきなり「打ち合わせ台本は捨てた!あんなネタはやらん」と豪語。パンツのチャックからシャツの端を出したり、靴下を半分脱いだりして「こんな芸人どうや!」と自虐的に日テレと同番組を避難。そして「おまえらオレが口だけやと思ってるやろ!」と言いながらステージ上で脱糞すると尻をまくったところでスタッフに取り押さえられる……だいたいこんな感じ。
もちろんこれまでもしたり顔で視聴者をいたずらにまどわしてきたテレビである。全てが台本どおりなのだと言われれば「あぁ、やっぱりか」と納得しうる。ただそんなことは抜きとしても、同放送は既存のテレビコンテンツの内容からすると極めて過激であり、強烈だった。それはある意味「最悪」で、ある意味「最高」でもある。もちろんそれは社会倫理と個人表現という矛盾するふたつの正義においてである。
ああいう芸人がいることも、ああいう芸風でやあることも、別に責められる事ではない。むしろ問題なのはそれを放送した日テレの姿勢にある。安易な数字取りなのか、それとも彼らは彼らで革命を起こそうとしたのか、その真意はわからない。ただ、いずれにせよかなり確信犯的であることには間違いはなく、またしてもその見えそうで見えないしたり顔だけが視聴者の中に残る。そして当の芸人はといえば?
お笑いにかぎらず、生まれた時から必然的にサブカルなものというのは必ずある。それに対してマスの頂点にあるテレビメディアがどのように接していくかはかなり難しい問題だ。結果的に喰いモノにしてしまうこともある。喰いモノにされてしまうこともある。ただ、そのせめぎ合いの中である種の実験が行われるのであれば、それがたとえゴールデンに不似合いな内容であっても、われわれはそれを受け止めて冷静に判断する必要があるだろう。ただ、今回の「エンタの神様」に関しては、プロデューサーだかだれだか知らないが脂ぎった業界人の浅はかな悪知恵ぐらいにしか受け取る事はできなかった。そういった意味できわめて不愉快な番組である。決してカンニングが不愉快なわけではない。(本当はまったく不愉快でなかったわけでもないのだけれど……)
01:41 | 固定リンク | | | トラックバック (12)
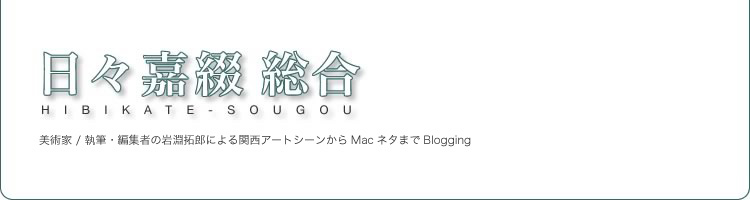





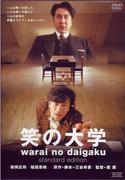

 プロフィール
プロフィール