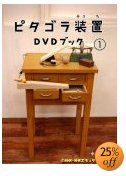2006年12月04日
地下のプールで韓日写真展「コミカル&シニカル」
208 SHOWCASE #018「写真にツッコミを入れる 〜 手の写真を〈読む〉」のゲスト、写真研究者の小林美香さんがプロデューサーをつとめる韓日写真展が来年1月に開催。会場はなんと大阪ドーンセンター地下プール跡。SHOWCASE #021ゲストの池田朗子さんも参加。これは行かなきゃ!
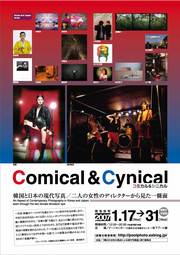
コミカル&シニカル
韓国と日本の女性のディレクターから見た「現代写真の一断面」
http://poolphoto.exblog.jp/
会 期:2007年 1月 17日 (水) 〜 31日 (水)
12:00〜20:00 月曜日休館
会 場:ドーンセンター(大阪府立女性総合センター)地下プール跡
大阪市中央区大手前1-3-49
TEL.06-6910-8615/FAX.06-6910-8624
観覧料:300円
連絡先:特定非営利活動法人 大阪アーツアポリア
TEL/FAX.06-6599-0170(担当:中西)
主 催:「韓日の女性の視点による現代写真展」実行委員会
<解説>
「コミカル&シニカル」とは、作品の中に共通して見られる特徴であり、社会や文化に対するある種の態度として表れている。作品は、日韓双方の文化の違いや共通点を発見させてくれることだろう。また会場は使われなくなったプール跡である。前例のない「おもろい」試みであり、「笑い」を誘発する要素が展覧会会場のいたるところに見出されることになるだろう。
<出品作家>
日本:浅田政志/小松原緑/みとま文野/佐伯慎亮/渡邊耕一/池田朗子/山下豊/梅佳代
韓国::申恩京/波惹/嚴殷燮/金奎植/金東鈴/盧順澤/金華用/河惠貞
<ディレクター>
パク・ヨンスク(写真家)/綾智佳(サードギャラリーAya)
<プロデュースチーム>
綾智佳/小林美香/中西美穂/仁科あゆ美
【関連イベント】
○ギャラリートーク
1月17日(水)18:00〜19:00 アーティスト+小林美香
1月18日(木)19:00〜20:00 アーティスト+パク・ヨンスク
1月19日(金)19:00〜20:00 アーティスト+綾智佳
1月21日(日)14:00〜15:00 アーティスト+金惠信
*各回予約なし、入場料が必要です。
○フォーラム 2006年1月20日(土)14:00〜17:00
参加費:1000円/定員100名
出演者:綾智佳、北原恵、小林美香、パク・ヨンスク、他
*ドーンセンター協催事業
mixi内コミュニティ「韓日写真展 コミカル&シニカル」
http://mixi.jp/view_community.pl?id=1614132
23:49 | 固定リンク | コメント (1) | | トラックバック (0)
2006年08月16日
澤田知子展「MASQUERADE」
2006年7月15日(土)〜9月3日(日)
キリンプラザ大阪
入場料 300円
オススメ度:★★★★
お見合い写真でブレイクした《撮られる》写真家・澤田知子の新作シリーズはキャバ嬢○人。正方形のフレームで埋められた壁はさながらKPOから目と鼻の先に乱立する風俗案内所のよう。それにしても、あいかわらずちょっと無理のある……これじゃ完全に「ぽっちゃりさんの店」だ。それでもずっと見ているとこれは好きとかこれは嫌いとかがでてくるから確かに面白い。全員同じ人物だと分かっていても、無意識のうちに物語をつくっていってしまう。今回の展覧会のテーマは「顔」ということだけれど、むしろ真実を写さない(特に女性に関しては!)写真というメディアの特性の方が際立っているようにおもえた。この点において、確かに彼女は《写真家》であると言えるかもしれない。
ちなみに下の写真は自分が投票したキャバ嬢とお見合い写真。どうです?
07:47 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (0)
2005年07月07日
「大(Oh!)水木しげる展」
会 期:8月4日(水)〜8月16日(月)
会 場:大丸ミュージアム 神戸
入場料:一般800円 大高生600円 中学生以下無料
オススメ度:★★★
荒俣宏と京極夏彦の共同プロデュース。水木しげるのこれまでの生涯を時間を追って追体験していくような内容。美術展というよりは回顧展(?)といった印象。各所に鏤められていた水木氏独特の語り口が、浮世離れした世界へ誘う。
時間が無くて残念ながら流し見だったのだが、単に漫画家・水木しげるに対してだけでなく、昭和30年代の紙芝居や貸し本システムが知れるという点においても面白い。あいかわらず原画展示という形態に関しては物足りなさは感じるが、商業展覧の企画としては十分の質と量。
機会があれば境港の記念館にも足をのばしたい。
11:42 | 固定リンク | | | トラックバック (9)
「栄光のオランダ・フランドル絵画展」
会 期:2004年7月17日(土)〜10月11日(月・祝)
会 場:神戸市立博物館
オススメ度:★★
あくまでもメインは「画家のアトリエ」である。このところのフェルメールブームにあやかった企画であるのは足を運ばずとも明らかである。しかしいざすべてがそこに向かうような展覧会の流れに身を投じてみると、逆に最後に肩すかしを食らうかもしれない。もちろんフェルメールがどうのこうのという話ではなく、それはむしろ絵画というメディアの取り上げ方の問題である。今どき「月の石」でもあるまいし、たかか数号の小さな絵に多くの人が殺到するのは、それ自体滑稽なことだ。そのことに気づくという意味において、同展覧は面白くなくはない。
個人的に興味を引いたのは、現在のわれわれの視点からして明らかに「おかしい」もしくは「上手くない」作品が多く出展されていたという点である。企画の内容的に、例えば遠近法の発見をまたぐようなかたちであったということもあるだろうが、それを差し引いても「おかしい」もしくは「上手くない」と感じられる作品が多かった。それらは大抵の場合、聞いたこともない作者もしくは明確な作者がわからないようなものであったが、それに比べてやはりファン・ダイクやルーベンスなどの有名な作家の作品は技術的にも表現的にも異なる次元にあるように感じられた。もちろん作家の知名度で評価するわけではないが、やはり名画と呼ばれるものは馬鹿にはできない。
ヤン・ファン・ダーレンの「バッカス」は違う意味でおかしかった。あれはただの酔っぱらいである。
11:42 | 固定リンク | | | トラックバック (30)
2004年10月06日
アトリエ・ワン「街の使い方」展 - 小さな家の設計から大きな年の観察まで
2004年10月2日(土)〜12月5日(日)
キリンプラザ大阪
キューレーター 五十嵐太郎(建築史・建築批評家)
入場料 700円
オススメ度:★★★
アトリエ・ワンの塚本由晴氏は、以前IMI主催で美術家の中村政人との対談で一度だけ話を聞いた。まるで建築家と思えないまるで大学生のような風貌と、飄々とした口調ながら鋭い指摘をする様子がとても印象的。目的も方法も違うが、美術という枠組みがこれまでにもまして知的に解体されようとしていている昨今において、彼らから学ぶべき物はおおいように思われた。
意外な事にアトリエ・ワンにとって今回は初の個展。内容は同ユニットの設計した狭小住宅「ミニ・ハウス」をカヤで1/1再現、その中で書籍や映像などの資料が展示されるというもの。空間性の体験という意味では面白いが、やはり見せ方としてはいささかものたりない。まぁ、展覧会というスタイル自体、建築の文脈から外れたもなのだから仕方ない。それでも彼らの仕事、というよりユニークな視点そのものの全風景を眺めるにはいい機会だった。
活動の部分で面白いと思ったのは、彼らの活動の中心がリサーチにあるということ。これは塚本氏が研究者であるという立場を考えると当然のなのかもしれないが、それ自体がひとつの作品として成立しているのは興味深い。もちろん彼らの仕事の本質は建築設計なのだが、もはやそれすらもプレゼンテーションの一部でしかないと感じてしまうほど、彼らの存在にはブレーンとしての意味合いが強い用に感じられる。
11:35 | 固定リンク | | | トラックバック (40)
2004年09月24日
トヨダヒトシ「スライドショー/映像日記」
2004年9月23日(祝)〜26日(日)
[NA.ZUNA part 1]・[NA.ZUNA part 2]・[The Wind's Path]
CAP HOUSE 神戸(神戸)
1,000円(1ドリンク付)
オススメ度:★★
スライドショーにデフォルトでBGMがつくようになったのは、もしかするとAppleの残した悪しき習慣かもしれない。時間軸に写真を並べてそれを投影する、それだけで写真はひとつの流れの中で新しいストーリーを語りだす。別に特別なことでも何でもないのだけれど、そういうことを当たり前をするのが実は一番難しい。この点においてこの作家は極めて潔い。ただしその潔さが作品を作品として成立させるべく正しい方向に導いているかどうかは微妙なところである。
誤解も含めてテーマは「旅」である。すくなくとも私にはそのように思えた。見知らぬ土地で見知らぬ人々とふれあうことで目覚める視線があることは、すでに誰でも知っていることである。それをいまさら作品として見せる、もしくは見せられるということに対しての疑問は多い。それにつけて昨今の写真ブームの後に、それでもなお作品化が可能な写真とはいかなるものか。写真という表現形態が本質的にメディアとの関わりを逃れられないとするならば、それについては潔いトヨダ氏に答えてほしかった問題である。あとプロジェクションという手法についてももう少し説得力が欲しかった。作者説明では「そこに有るのに触れる事が出来ない距離感」とのことだったが、個人的には納得するにはいたらなかった。
ただ、そういったことを考慮しても、スライドショーをひとつの表現形態として突き通そうとするトヨダ氏の潔さについては今後の期待もこめて評価したい。
11:40 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (31)
2004年09月04日
「6人の作家/articulation 2004」
2004年9月4日(土)〜25日(土)
今井祝雄・植松奎二・河崎晃一・倉貫 徹・藤本由紀夫・百瀬 寿
ARTCOURT Gallery(大阪・天満橋)
入場無料
オススメ度:★★★
作品の評価において「凛とする」という言葉を用いたのは「ノンポリおおさか・(展)」でご一緒した松村 アサタ氏だったが、それは同グループ展を言い表す上で適切な言葉のように思われる。極めて「凛」とした展覧会。
すでにキャリアの長い作家たちによるグループ展である。そこにコンセプト上の安易なすりよせなどは感じられない。むしろそれぞれがそれぞれの仕事を全うしているように感じられる。「凛」というのは、その結果として浮き上がってきた印象だ。それこそが本展をグループ展として成立させているように感じる。
中でも植松奎二と藤本由紀夫の力は大きいように思われるが、このあたりは好みの問題かもしれない。逆にいまいちピンと来なかったのは大量のチラシを丸めた今井祝雄のインスタレーションで、この作家に関しての予備知識はとくにないが、一見すると作品そのものの力より空間に頼る部分が大きかったように感じられた。河崎晃一の小さめの造形は、本人を存じているせいだろうか、いつも人物とのギャップが興味深い。倉貫徹の水晶を用いた平面は、単純な構図の中に素材の差異による独特の緊張感があって興味深かった。
11:46 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (38)
2004年08月01日
西野康造「空のかたち」
2004.7.10(土)〜 8.29(日)
ARTCOURT Gallery(大阪・天満橋)
入場無料
オススメ度:★★★★
自分が言葉を使った仕事をしているせいもあるだろうが、私は既存の美術的言語に対してどうも斜に構えて見ているような節がある。ここで言うところの言語とは表現における形態のことだが、とりわけ彫刻に対するそうした想いは強い。例えば、無骨な鉄の固まりがほんの少し反りながらそこに存在しているということ。その正当性についてここで触れることではないが、ただそれが表現として優れた言語として成立しているかということに関してはかなり疑問だ。
西野康造という作家に対する予備知識はない。ただ今回の作品だけをみてその仕事を自分ありに評価するとすれば、前述の言語という意味合においてそれは抽象的な形をとっているにもかかわらず非常に雄弁だった。「空のかたち」といういささかスイートなタイトルも、本体の的をえながらもいい具合で印象を中和させている。こういう作品にたまに出会えるので、やっぱり彫刻もそれほど無視はできない。
高さ10メートルをこえる輪や複雑に連結されたモビール状の作品。大きいわりにアルミやチタンといった素材のせいか、いい意味でそれほど重量感はない。細いフレームで組み合わされた作品も、素材自体のしなやかさによって、空調の風を受けて振動している。丘の上にあって風になびくような印象。いわゆる金属彫刻に対する印象がここちよくずれていくのがおもしろい。
これらの作品からわれわれが受け取るものはかなり具体的な情景やシーンである。作品の存在の仕方自体を考えればそれほどの新しさも驚きもない。ただ、あえて遠回りな手法をとりながら最後にスイートな情景に回帰していくという面白さは美術としてひとつの正解だし、なによりその分かりやすさに私は純粋に心を動かされる。
01:40 | 固定リンク | コメント (0) | | トラックバック (11)
2004年07月31日
近藤晃弘「死線上のバンパイア」
2004.7.12(月)〜 7.31(土)
ギャラリー wks(大阪・西天満)
入場無料
オススメ度:★★
近藤晃弘、79年生れ、大阪芸術卒の若い作家。
内容はホワイトキューブの会場が血しぶきで染められているというもの。意外にもギリギリのところでグロテスクではない。むしろ赤く染め上げられた空間には不思議と閉鎖感がなく、ほんの少し心地いい。ロケーションも考えればとあるマンションの一室の惨殺劇となっても不思議はないが、どこか最後の一線でそういった下世話さを踏みとどまらせている。
ただし、やはりこういった単純な構成のインスタレーションは、よっぽどでないと物足りなさを感じずにはおれない。まぁはっきりいえば安易である。がんばっていただきたい。
なお、ギャラリーwksには初めておとずれたが、マンションの11Fでもここまでできるかとちょっと関心。アクセスは決していいとはいえないが、スペースとしてはなかなか面白い。後日、ゆっくり訪れよう。
01:39 | 固定リンク | | | トラックバック (5)
田名網敬一 × 宇川直宏「DISCO UNIVERSITY」
2004.6.5(土)〜 8.1(日)
KPOキリンプラザ大阪(大阪・心斎橋)
一般700円/学生500円(中学生以下無料)
オススメ度:★★★
宇川直宏という人についてのイメージは、その名前との出会いから、いまだにMOM'N DADの主催者という印象が強い。20分ほどのハナタラシのものを壊すだけのライブと、ディック・ハイマンなどのスペースエイジ・バチェラーパッド・ミュージックの抱き合わせ(?)コンピを私はリアルタイムで手に入れ、そして今でも持っている。
田名網敬一と宇川直宏のコラボレーションということなので、てっきり一緒にペインティングをしたりコラージュしあったりといった内容を想像していたが、実際は田名網氏の過去の作品の展示を宇川氏がディレクションするというもの。そういう意味では若干期待をすかされた感じではあるが、田名網氏のことをほとんど知らなかったので、全貌を知るいい機会となった。
作風に関しての詳細な解説は省こう。個人的にはああいった70年代を感じるような毒っけのあるイラストレーションはそれほど好きではないが、もはやそういった好みをどうのこうのいう以前に、作品の多さと、個々の作品持つ情報量に圧倒された。こういった作品に大して、もはや解釈という行為はそれほど意味をなさないように思う。作家の爆発するようなエネルギー量や、それによって生まれる疾走感のような感覚は、もはや理性の領域でうけとめられるべきではないだろう。この点に関しては宇川氏にも同じことが言えるかもしれない。とにかく失踪する2人である。
宇川氏による展覧会全体のディレクションは正直少し物足りなさを感じた。会期中にクラブイベントを実際にそこで行うといった試みは風俗的な文脈を美術に持ち込むと言った意味では評価できたが、展示そのものにはあまりそれが見受けられなかった。
01:38 | 固定リンク | | | トラックバック (10)
2004年07月25日
山崎つる子「リフレクション」
2004.7.12(月)〜 7.31(土)
芦屋市立美術博物館
一般500(400)円、大高生400(320)円
オススメ度:★★★★
具体というと身体性を重視したような派手なアクションやハプニングといったことを連想する。しかしが同グループの一側面でしかないということは、すでに先の「具体回顧展」(兵庫県立美術館)において語られたことである。今回の山崎つる子展はその内容をあらためて立証するためのいい機会だ。
かつて"confusion"という言葉によって表された山崎つる子の抽象絵画は、今もなお十分に混乱を極めているように見える。あらゆる要素において安定と調和を拒否するような作品からは、もはや禁欲的なものすら感じられる。デタラメであるために繰り返される葛藤と省察。その態度はある意味で私たちが持っている具体のイメージと正反対のものであるように思える。ただ面白いことに、そこからなにかから解き放たれたいとする苦痛はまったく感じられない。
作品の変遷もなかなかデタラメである。突然「title」(もちろん「untitled」ではない)という題名で具象画を描いてみたり、かと思えば転がるビー玉に光を通すような普通にきれいな作品もある。あまのじゃく、そんな言葉をイメージする。いつも対局するものの間を行き来しながら、けっきょく何にも束縛されないお嬢様。そういえば彼女は芦屋生まれの芦屋育ち、清心女子出身のねっからのお嬢様だったか。まぁ、特に関係はないだろうが。
展覧は彼女の活動を理解する「redlection」「color」「confusion」「metallic」「stripe」「title」の6つのキーワードによって構成。あえて異なる次元で視点を混乱させたのも意図的かもしれないが、そこはもうちょっと系統立ててみてもよかったかもしれない。
01:39 | 固定リンク | | | トラックバック (14)
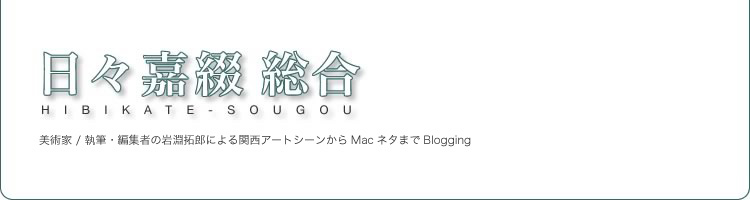



 プロフィール
プロフィール